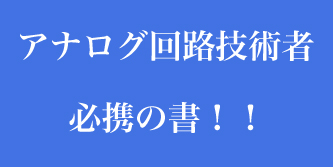インピーダンスと複素数
それでは前ページに引き続き、インピーダンスが普通の抵抗とは違う2つ目の項目、なぜ複素数が含まれるか、を考えたいと思います。複素数をわざわざ使うのは、容量とインダクタが、物理的に抵抗とは全く違う性質を持っていることに由来します。しかし幸運なことに、その違いは、電流と電圧に伝わり方に「遅延(タイムラグ)」が生じるだけですんでいます。これは、アナログ回路設計者にとって本当に幸運なことでした。抵抗値に加えて、タイムラグというパラメータをたった1つ追加するだけで、容量とインダクタの性質を正確に表現できたのです。(そうなるように容量とインダクタという概念を定義したとも言えます。)
抵抗器、容量、インダクタの各素子は、抵抗値とタイムラグという2つのパラメータを持っています。それぞれのパラメータは別々に計算することが可能です。例えば、抵抗 R とインダクタ L を直列につなげた場合の合計の抵抗値は、√(R^2 + (ωL)^2) [Ω] です。タイムラグは、tan^-1 (ωL/R) / ω [s] です。わざわざ複素数を持ち出さなくとも、このように計算することができます。抵抗1個とインダクタ1個だけの簡単な回路構成であれば、それほど難しい計算式ではありません。しかし、これに容量が加わったり、抵抗が何個も入ってきたりすると、どれほど難解な式になるか、考えるだけでも吐き気がしてきます。
そこで人類は、複素数の概念を回路に応用することにしました。複素数は、抵抗値とタイムラグの計算を簡単にしつつ、2つのパラメータをほぼ同時に計算してしまう優れものなのです。なぜ複素数かというと、その理由は1つだけではありません。第一の理由は、複素数が「ベクトル」の仲間だということです。ありきたりではありますが、「風」がベクトルのよい例です。風は、東西方向と南北方向の強さの足し算で表されます。東西を X 軸、南北を Y 軸としましょう。X 軸方向の風の強さが 3 m/s、Y 軸方向が − 4 m/s の場合、風の強さは、ピタゴラスの定理から √(3^2 + 4^2) = 5 m/s、風の方向は、tan^-1 (−4/3) 度になります。このようにベクトルは、風の「強さ」と「方向」を同時に扱うことができます。回路の抵抗値とタイムラグは、ちょうどこの強さと方向(角度)に対応するのです。2次元ベクトルを使うと、この2つの量を同時に計算できて便利です。
2次元ベクトルの定義は、独立した2つの要素の足し算で、全ての座標が表現できる、ということです。(X, Y) で表すベクトルの場合、例えば 3●X − 4●Y のように X と Y だけで全ての座標を表現できます。X と Y はお互いを何倍したとしても、互いを表現できません。X = A●Y は、A にどんな数を入れたとしても成り立ちません。よって、X と Y は独立と言えて、(X, Y) はベクトルたる資格を持ちます。複素数も同様なことが言えます。X = 1、Y = j とすると、さきほどのベクトルは 3●1 − 4●j となります。j を何倍したとしても実数にはなりえませんので、実数と虚数は互いに独立しています。よって、複素数もベクトルなのです。
それでは、なぜ (X, Y) の普通のベクトルを使わずに、複素数を持ち込むのでしょうか。この答えが、複素数を導入する2つ目の理由です。複素数というベクトルをわざわざ使うのは、複素数が特殊なベクトルだからです。それは、虚数の定義である j^2 = − 1 に由来します。さらに4乗の場合は、 j^4 = 1 です。お気づきとは思いますが、4回掛けると 1 になるため、何もしなかったことと同じになります。これはまさに「回転」の概念を表しています。1回転は、360度(あるいは 2π)ですので、j 1個は 90 度に対応することになります。このように、複素数は、回転を簡単に扱えるという特徴を持つベクトルなのです。
そして電気回路は、回転の概念と非常に良い相性を示します。電気回路を扱う時に普通の設計者が興味を示すのは、入力信号に対してどのような出力信号が得られるか、です。入力信号は、1クロックだけのパルス信号だったり、三角波だったり、何の形とも表現できないようなめちゃくちゃな波形だったりと様々です。しかし、いかなる形の波形でも、様々な振幅と周波数のサイン波を無数に足し合わせることで表現できるという有り難い理論が世の中に存在します。(発散するような変な波形は扱えませんが。)これを「フーリエ展開」といいます。この理論を前提とすると、結局は入力信号がサイン波の場合だけを考えておけば、他の波形のことも考えたことになってしまいます。よって、回路の理論では、とりあえず入力波形がサイン波だと仮定してしまうのです。そしてサイン波は、回転を射影したものであるという厳然たる事実があります。(高校の数学の教科書に書いてあります。)回転を扱いやすい複素数というベクトルをわざわざ選択したのは、このような背景によります。
回転の角度は、回路のタイムラグに対応します。サイン波と複素数ベクトル座標上の回転の関係がイメージできれば、これは簡単に理解できます。入力信号 A sin (ωt) をある回路に入力したところ t1 というタイムラグが生じて A sin (ω (t −t1)) という出力信号が出てきたとします。変形すると A sin (ωt − ω t1) です。入力信号と出力信号をそのままベクトル座標上に示すと、両者は角度 ω t1 の差を保ちながら回転します。同じタイムラグだったとしても、サイン波の周波数によって 1/4 周期だったり、1/10 周期だったりと、そのタイムラグに対応する角度が変わりますので、角度は t1 に ω が掛かった形になります。そして、この角度を「位相」と呼びます。(別に角度という呼び名のままでもいいような気がしますが、それではサイン波を想像しづらいということで位相という呼び方をしているのでしょうか??回路では、回転よりもサイン波の方が主役ですからねぇ。)
それでは、j が 90 度分のタイムラグに対応する、ということを踏まえて、改めて各素子のインピーダンスに着目してみましょう。容量のインピーダンスは 1/jωC です。インピーダンスは R の代わりに Z という記号を使いますのでオームの法則は V = I Z と書けます。容量の場合は、V = 1/jωC x I = − j/ωC x I です。−j ということは− 90 度に対応しますので、サイン波の電流 I を容量に入れると、容量の両端の電圧 V は 90 度分遅れたサイン波になります。単に 1/j ( = -j ) をかけ算するだけで 90 度の遅れを表現できるというのは助かります。一方でインダクタの場合は、 V = jωL x I です。すると、V は I に比べて 90 度分だけ進んだ波形になります。ここで1つ注意が必要なのは、進んでいるからといって別に因果関係が破れているわけではない、ということです。無限に長い時間、サイン波を入れ続ける中で、V と I の波形を比較すると V の波形の方が 90 度分進んでいるように「見える」だけです。現実の物理現象では、I = 1/jωL x V = −j/ωL x V と I と V の関係を交換した方が分かりやすく、I が V に対して 90 度分遅れるという因果関係になります。最後に残った素子は、抵抗 R です。これは j を含みませんので、抵抗のみで構成される回路にサイン波を入力した場合、タイムラグは生じません。
抵抗、容量、インダクタが混じ合った回路の場合は、それぞれのインピーダンスを合成する必要があります。容量と抵抗を直列に接続した場合、そのインピーダンスは、1/jωC + R です。この複素数ベクトルから合成後の抵抗値とタイムラグ(位相)を計算します。実数部と虚数部に分けると (R, −1/ωC) です。抵抗値はベクトルの大きさなので √(R^2 + (1/ωC)^2) です。位相は tan^-1 (1/ωRC) です。計算の手順は、(1) インピーダンスを普通の抵抗だと思って計算、(2) 出来たベクトルから抵抗値と位相を計算、となります。計算過程で複素数を使ってはいるものの、算出結果の抵抗値と位相には虚数は含まれません。複素数に特に深い物理的な意味を持たせているわけではなく、あくまで計算を楽にするためのツール、計算過程の黒子でしかないことにご注意ください。インピーダンスの複素数の成分をあえて「リアクタンス」と呼んでそれなりの物理的な役割を与えることもありますが、これは複素数を扱うこととは無関係です。普通の抵抗と別の軸を持つベクトルの成分でありさえすればよく、(X, Y) のベクトル座標でもかまいません。
ちなみに、これまで説明を省いてきましたが、ここで計算した複素数のベクトルのことを「複素インピーダンス」と呼び、その大きさによって表される抵抗値のことを「インピーダンス」と使い分けることもあるようです。一応補足しておきます。
ここまでがインピーダンスの概要と、その中に複素数がなぜ登場するのかというお話でした。しかし、ここまでの説明で、微分方程式、ラプラス変換、オイラーの公式というキーワードが全く登場しなかったことにお怒りの方もいらっしゃるかもしれません。それに、なぜインダクタと容量のインピーダンスが jωL と 1/jωC になるかもご説明していません。そこで、もう少しだけ、このテーマを続けてお話させていただきたいと思います。
「ラプラス変換と複素数」へ